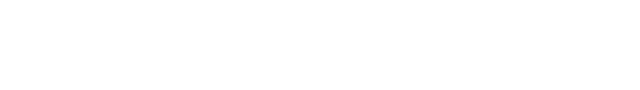腎がん
おしっこを作る腎実質にできる悪性腫瘍のことを腎細胞がん(腎がん)と呼びます。その中でも8割以上を占めるのが淡明細胞型腎細胞がんといいます。その組織像が免疫染色にて淡明な細胞質を有するがん細胞が増殖していることからこの名がついています。私が研修医のころには進行した転移性腎がんには効果のある抗がん剤はなく、インターフェロンやインターロイキンを使用するサイトカイン療法が使用されるくらいでその効果も極めて限定的でした。ちょうど研修医で泌尿器科を選択している時期に、今では腎がんのみでなく多くの進行がんでも治療の柱の一つである分子標的薬が適応となり私が数ある診療科の中で、泌尿器科に決めた理由の一つも実はここにあります。手術や手技が好きで、また患者さんを診断から治療まで一貫して診られることに一番の魅力を感じていましたが、転移性腎がんにおいて、このような新しい治療が、そのがんの特性にもよりますが他科に先駆けて導入され、治療効果を認めていたことにますます興味が湧いたのでした。話は脱線してしまいましたが、その後、腎がん治療領域はさらに進歩し、ノーベル医学生理学賞を本庶先生が受賞するきっかけとなった、がん免疫チェックポイント阻害薬(オプジーボ)も、腎がん治療の中心をなし、前述の分子標的薬との併用療法が標準治療になり、最新のエビデンスは日々蓄積されています。私自身、今までの泌尿器科医人生の経過とともに(腎がん分子標的薬とほぼ同期です。)新しい腎がん治療が出るたびにアップデートを行い、その都度、患者様にあった治療を選択し経験を蓄積して参りました。前置きが非常に長くなりましたが、腎がんについてもう少し詳細なことを述べていきます。
1. 疫学について
好発年齢は50歳~60歳で比較的若いと言われています。また男女比は2~3対1で男性に多くみられます。近年は人間ドックや検診の普及で腹部エコーやCTなどで早期に発見、治療が可能になっています。芸能人で人気芸人さんだけでも、3人ほど腎がんを公表して皆さんにとっても身近な疾患になっているのではないかと思います。また長期間の透析患者様にみられる後天性嚢胞腎は腎細胞がんの発生頻度が高いとされております。
2. 病因について
全固形癌の中で原因となる遺伝子異常が最もはっきりと解明されているのが淡明腎細胞がんおけるVHLがん抑制遺伝子になります。VHL蛋白はHIF(低酸素応答因子)の分解を抑制していますが、変異よりその働きが不活化するとHIFが分解されず活性化され、血管内皮増殖因子(VEGF)が過剰に産生されます。腎細胞がんはこのVEGFを分泌し血管内皮の増殖を促すことで腫瘍が増殖します。血管新生を阻害する分子標的薬が腎がん治療で研究が進められ治療に応用されるようになった経緯はここにございます。
3. 症状について
早期は無症状であることがほとんどです。私が研修医の頃は、腫瘍の増大よる血尿や骨転移よる疼痛なども散見いたしましたが、血尿や疼痛、腫瘍の触知などを認める頃には、それなりに癌が大きくなっていると考えられます。これらの症状では肉眼的血尿が診断のきっかけになることが一番多いです。とはいえ腎細胞がん全体ではやはり検診よる異常所見が圧倒的に主訴としては多く、8割ちかくは症状のない偶発腎がん(検診等で偶然に指摘)といわれています。
4. 診断について
前述のとおり、検診での超音波検査(腹部エコー)異常で受診されることが多く、当院でも再度エコー検査を行います。そこでも腎がんが疑われた場合には点滴で造影剤を入れながら撮影を行う造影CT検査が必要となります。造影剤のアレルギーや腎機能が悪く造影剤を使用できない場合はMRI検査で代用することもあります。当院で腎がんが疑われた場合は近隣の連携病院にCT検査やMRI検査を予約できますのでご安心ください。またCTやMRIで腎がんの診断を行い、次に転移していないかどうかの検査(CTや骨シンチなど)を行いステージを確定する流れになります。腎がんにはその診断に有用な腫瘍マーカーが現状ないのですが、転移を伴う進行がんはHb(ヘモグロビン)の低下、LDHの上昇、CRPの上昇、Ca値の上昇など異常を認めることもあり、後ほどの薬物療法を判断する上での再発のリスク分類にも有効な指標となります。
5. 治療について
根治療法は早期がんでは手術療法となります。手術の方法も開腹手術、腹腔鏡手術、ロボット支援手術とその選択肢も多岐に渡り、癌の大きさや部位などを考慮し選択されますが、最近は腹腔鏡手術もしくはロボット支援手術を選択されることが多いです。また腫瘍の大きさよっては全摘術(癌のある方の腎臓を全てとる)ではなく部分切除(がんの部位のみをくり抜いて腎を温存する)も選択可能で、ロボット支援手術による腎部分切除も増えています。腎を温存する腫瘍径に関しては4㎝未満のT1a期であれば十分に根治性を担保できることがエビデンスで証明されており議論もないと思いますが4㎝以上7㎝未満のT1b期でも、その治療成績が問題ないことが神戸大学を中心とした臨床研究でも示されており4cm以上でも部分切除も検討し腎を残せることも多いです。7cmを越えるものや腎盂といって尿路の通り道に腫瘍が浸潤しいている場合は全摘になります。またそのサイズが非常に大きく周辺の臓器に浸潤している場合や、静脈(腎脈や下大静脈など)に腫瘍塞栓を認める場合は開腹術を行うことになります。このように手術で完全とり除くことができれば完治できる癌であるために早期発見、早期治療が重要であるのは周知の通りです。
次に転移性腎がんの治療についてそのエビデンスや私見を述べて行きたいと思います。腎がんの薬物治療は前述のとおり15-6年前まではサイトカイン療法しかなかったのですが、分子標的薬(4つのチロシンキナーゼ阻害薬と2つのmTOR阻害薬)の登場より、その生命予後は格段に延びました。副作用は従来の抗がん剤で認めた吐き気や脱毛などとは違い高血圧や皮膚症状、下痢などが代表的なものですが、多くは症状に対する対症療法でコントロールし長期に使用可能なことが多いです。その後、免疫チェックポイント阻害薬(2の抗PD1抗体薬と1つの抗PD-L1抗体薬、1つの抗CTLA-4抗体薬)が使用可能になり、単剤使用ではなく最初から併用することが、現在の治療ガイドラインでも推奨されています。これだけの数の分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬があり、その組み合わせになると非常に複雑となりどれを使っていいのか泌尿器科専門医でさえ意見が分かれることも少なくありません。診療ガイドラインではもちろんその推奨薬の組み合わせの指針は示されていますが、同列に並んでいます(いずれも推奨グレードAと記載あり、Aが複数あるということです)その理由はそれぞれの治療薬の臨床試験は対象患者が全くの同一集団であることが不可能であり、結果を横並びで比べてもあまり意味がないからです。私自身は今まで多くのがん拠点病院での臨床経験を有し、エビデンスを元に、治療薬の成績や副作用などを十分に説明し患者様個々の特徴にあった治療方針をご提示して参りました。とはいえ、中には選択に悩ましいこともあり、病院勤務時代は先輩や同僚とともに議論し、その都度、患者様に最善の治療を提示し行って参りました。また治療だけでなく、身体的、精神的なものも含めた副作用マネージメントも行ってきた経験を今後は生かしていきたいと思います。他の病院(多くは手術を行った病院でその後に薬物療法を開始、継続しているかと思います)で腎がんの薬物治療中の方でも、どんな些細なことでも構いませんので、なんなりとかかりつけ医としてご相談くださればと思います。