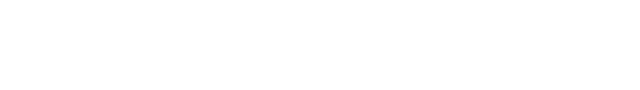膀胱がん
おしっこを貯める袋状の臓器である膀胱に発生する癌を膀胱がんといいます。男女ともに発生しますが、その頻度は男性が女性の約3倍ほどです。症状は肉眼的血尿が多く、その場合の血尿は痛みを伴わずまた放置しても消失するのが特徴的です。癌が膀胱の粘膜内のみであれば尿道から内視鏡を入れて行う経尿道的手術で治癒可能ですが再発を繰り返しやすいことが特徴です。粘膜を超えて膀胱の筋肉まで癌が広がっていると抗がん剤治療や膀胱全摘(全て取り除く)が必要になります。また転移を認めた場合には抗がん剤治療になり完治を見込めなくなるので、早期発見、早期治療が大事です。そのために痛みのない血尿を認めた場合は放置せず必ず泌尿器科を受診しましょう。それではもう少し詳しく膀胱がんについて説明します。
1. 原因について
発癌の危険因子として化学物質、喫煙、尿路感染症(北アフリカに分布するビルハルツ住血吸虫)などが言われています。化学物質は染料に用いられていた芳香族アミンが暴露から20年前後の長期経過を経て膀胱がん発生に関わると言われています。日本では2015年から有害物質を有する家庭用品の規制に関する法律で24種類の芳香族アミンが規制されています。またビルハルツ住血吸虫による膀胱がんも日本では現実的ではないので、ここでは喫煙のリスクを主に説明します。喫煙者は非喫煙者に比べて10倍近く、膀胱がんになる相対危険度が高く、膀胱がん全体の4割近くは喫煙が原因で発生していると推測されています。
2. 症状について
症状は前述のとおり、痛みを伴わない肉眼的血尿が最も多いです。症状がはっきりしているのですぐに受診いただき詳しい検査をすれば早期発見が可能です。ただし血尿は一旦自然に治まることもあり、注意が必要です。これは腫瘍がなくなっている訳ではなく、腫瘍からの出血が一時的に自然に治まっているだけです。また腫瘍が進行した場合は膀胱内に腫瘍が充満すればその尿が貯められる容量が小さくなり頻尿を認めたり、膀胱の出口を塞いでしまえばおしっこが出しにくくなったりします。また膀胱がんに膀胱炎を合併すると排尿時痛を来すこともあり膀胱炎治療で尿中の白血球が改善したのも関わらず赤血球を持続して認める場合などは膀胱がんの存在も念頭にいれる必要もあります。
3. 検査について
まずは尿検査にて血尿の原因を検索します。顕微鏡で赤血球を認めるか確認し、また尿の中にがん細胞がいないかの尿細胞診を提出します。その後に腹部超音波エコー検査で膀胱を観察し腫瘍を確認します。大きな腫瘍ではこのエコー検査でも確認できることもありますが腫瘍が小さい、もしくは膀胱内に尿が貯まっていない場合ははっきりしないことも多々あります。最終的には膀胱鏡といって膀胱内に尿道から内視鏡を挿入し肉眼でその腫瘍の確認が必須となります。当院では細径の軟性ファイバーを使用しており、また挿入前にはゼリーの麻酔を尿道および内視鏡に塗布しますので、疼痛は最小限で行えます。異物を挿入するので全く痛みがゼロではないですが、丁寧に痛みがないように行いますのでご安心ください。
4. 診断について
膀胱がんは前述の内視鏡所見でおおよその診断がつきます。カリフラワーのような見た目で茎がある腫瘍(有茎性乳頭状といいます)や、全体的にベタッと広がる茎のない塊のような腫瘍(広基性腫瘍といいます)などは膀胱がんを強く示唆します。また腫瘍ははっきりしないが粘膜が全体的に赤いものは上皮内癌の可能性が高くなります。筋肉まで腫瘍が到達している可能性が少し高いものに関しては術前にMRI検査を行うこともあります。ただし確定診断はいずれにせよ、経尿道的な内視鏡手術による組織診断が必要です。この経尿道的な手術はもちろん治療ですが診断も兼ねる手術となります。その組織型や進行具合によって追加の治療が必要かどうかを診断します。組織は9割以上が尿路上皮がんで残りの5%は扁平上皮がん、腺がんは1%以下といわれています。また進行具合とはがんが粘膜に留まるか、筋肉まで広がっているかでステージが1期か2期以上になります。筋肉まで広がっていた場合はそのがんが他の臓器やリンパ節に転移していないかをCTや骨シンチ検査で検索し最終的なステージングを含めた確定診断になります。
5. 治療について
診断でも述べましたが、まずは経尿道的腫瘍(TUR-BTといいます)で肉眼的には腫瘍を全て切除します。この手術は部分麻酔もしくは全身麻酔で行いますが手術時間は概ね30分から1時間程度のことが多いです。ただしその腫瘍が多発し、サイズが非常に大きい場合などは時間がそれ以上かかることもあります。術後は多くは外来で結果を聞いた上で、追加治療が必要かどうか判断します。上皮内癌という組織が検出された場合は膀胱内にBCGを注入する方法を外来で継続します。また粘膜内に留まっていたものの悪性度が高かった場合は再度削った場所を同様の手術で癌の取り残しがないかの確認を行います。残念ながら筋肉まで進行していた場合は経尿道的手術では不十分であり、多臓器の転移がないかの確認に移ります。転移がなければ標準治療は術前に抗がん剤を2〜3コース行い、膀胱全摘術(膀胱自体を全て取り除く手術)となります。手術の方法は開腹手術、腹腔鏡手術、ロボット支援手術といずれも可能ですがロボット支援で行うことが多くなっています。また膀胱はおしっこを貯める袋ですから取り除いた後は代わりの袋が必要で、それを尿路再建といいます。具体的には皮膚に尿管から直接おしっこを排泄する尿管皮膚ろう造設や、腸を用いてバイパスを作成し皮膚から排泄する回腸導管造設、または腸を用いて体内に代用膀胱を作成する新膀胱造設となります。前者2つは失禁型で新膀胱のみは自排泄型ですが、その適応は尿道に腫瘍が残存しないなど制限があり、造設しても自尿を認めず、カテーテルで排尿管理が必要なこともあります。次に転移してしまった膀胱がんについての治療を簡単に説明します。膀胱がんの抗がん剤治療は1983年にシスプラチンというプラチナ製剤が開発され、その後の2004年にM−VAC療法(メトトレキサート+ビンブラスチン+ドキソルビシン+シスプラチン)といって4剤も併用する抗がん剤治療(化学療法)が行われてきました。2008年にはようやくそれが2剤で済むGC療法(ゲムシタビン+シスプラチン)が同等の成績と認められ広く使われてきました。シスプラチンは腎機能が悪い方には使いにくく2014年にはGCa(ゲムシタビン+カルボプラチン)が使用されていますが、いずれもその成績は必ずしも十分なものではなく、それら初回治療に効果がなくなった場合の2次治療に難渋していました。つまり30年近くプラチナ製剤を用いた化学療法のみで、新規の薬剤が生まれなかったのです。そこで2017年に免疫チェックポイント阻害薬が登場し、ようやく2次治療以降の有効な選択肢ができました。具体的にはPD-1/PD-L1抗体であるペンブロリズマブやアベルマブがそれぞれ2017年12月と2021年2月から使用可能になり、2021年9月からは、抗体薬物複合体といって、がん細胞に選択的に作用する抗がん剤治療であるエンホルツマブ ベドチンが使用可能となり、今後は併用療法も含めたさらなる治療薬の改善、成績の向上が待たれています。